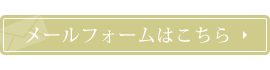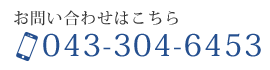このページをご覧の方への大切なお知らせ
サイト移行に伴い、このページのアドレスは2024年2月末をもって変わりました。
新しいページ(カテゴリーページ)のアドレスは、次のとおりです。なお、移行後のアドレスには自動的に切り替わりません。
https://satohi-office.jp/kensetu.html
このカテゴリーページから申請の要件、申請手続き、変更手続などのエントリーページをご覧になることができます。
また、お気に入り登録されている方は、お手数をおかけしますが、上記の新しいアドレスに変更して下さるようお願い申し上げます。